麦穂9月号巻頭言 オミナエシ 主任司祭 細井保路
2025/9/14
オミナエシ 主任司祭 細井保路(ほそいやすみち) 「秋の七草」は万葉集の山上憶良の歌に由来するといわれています。7つ全部を思い出すために、色々な覚え方があるようですが、私は勝手に自分で考えた覚え方が頭に入っています。 「ハギ・キキョウ/ススキ・ナデシヨ,オミナエシ/フジバカマ・クズ」。この覚え方だとスルスルと名前が出てくるのです。ススキのことは、七草を数えるときには、尾花(オバナ)と表記するのが一般的ですが、ススキの方が身近な感じがするので、勝手に「ススキ」に置き換えています。 萩や芒や葛は庭で鑑賞するには持て余してしまうし、カフラナデシコ、フジバカマ、園芸種でないキキョウなどは、ほとんど見かけなくなってしまいました。オミナエシだけが、七草を代表して教会の庭でも咲いてくれています。本当は、遠目にもその優しい黄色が目につくように、野原に群生しているところを見ることができたら素晴らしいのですが、庭の小さな一角でも、すっくと伸びた茎の先で揺れている花を見ると、秋の野山の空気を感じられる不思議な花です。来年はもっと茎の丈が高くなってくれて、もっと大きな野山を思い出させてくれることを期待しています。 学生時代に北海道の石狩の海岸にススキを見に行ったことがあって、それ以来、一株のススキを見ても、その背後に、見渡す限りの芒の原を感じる気がします。葛の花も、山の中で木々に絡みついて咲き誇っている景色に出会うと自然の大きさに感動します。萩の群生はなかなかお目にかかれませんが、奈良の百毫寺の萩は野趣に溢れていて、この季節になると見に行きたくなります。 秋の花は、それぞれの花の背後に広がる自然の大きさを感じさせてくれます。一つひとつの存在には、大きな背景があり、その大きな背景がすべてを包み込んでいることを、そこにある小さな花が示してくれているのです。これは、神さまが造られた世界のあり方です。ちいさな命は、大きな自然の営みのから生み出され、その背後に神さまのさらに大きな手があり、すべてがそれに包まれていることを伝えているのです。オミナエシが風に揺れるたびに、花の命を生み出している豊かな自然という背景と、それを治められる神さまのはからいを感じとることができます。人も全く同じで、そこに居る一人の人を支えているものがどれほ大きく豊かであるか、しかも同じ神さまの御手に支えられているのだということを、いつも思い出していたいと思います。
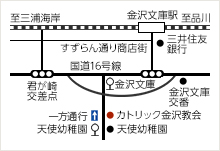


 045-783-3524
045-783-3524